| 一通りの見学を終え、ラボの片隅で話し合う3人。そろそろロボットによっては帰り支度を始めたようだ。話は自然と建設現場でこれらロボットを使えないかという話題になった。 |
 |
B主任: |
うちで、今すぐにでも働いてもらいたい機体がわんさかあったで。 |
 |
 |
C主任: |
そうだね。建築でも蛇型は配管検査などにぴったりだと感じたよ。 |
 |
 |
B主任: |
土木的にも彼ら、パワーに制約があるからの、やはり検査系がメインになるやろな。ただ、心配もある。 |
 |
 |
D職員: |
逆に建設機械にこれら制御技術を転用すればいいんじゃないですか。 |
 |
 |
B主任: |
それも解決策のひとつやけど、言いたいのはそこやない。まだまだロボット達がタフじゃないということや。少なくとも土木の現場ではな。 |
 |
 |
C主任: |
電源コードかい? |
 |
 |
B主任: |
それもそや。けど一番の問題は過酷な環境やな。土と水は手ごわいで。 |
 |
 |
D職員: |
でも、小柳先生の04号機デイジーなどの防水型もあるんだから、問題ないんじゃ・・・。 |
 |
 |
B主任: |
まだまだ青いのぉ。例えばカメラ自体が防水ケースに守られてても、前のガラスが曇って機能しなかったりするんや。あとはな細かな砂が擦動部分に入り込んでな、大変なんや。 |
 |
 |
D職員: |
ど、どこでそんな経験を。 |
 |
 |
B主任: |
昔シールドマシンの各種自動化に関係していたことがあるんや。そこでセンサーや機器にずいぶん悩まされたんでな。 |
 |
 |
C主任: |
それもそうだけど、喫緊の課題としてはパワーソースじゃないか。電池では作業時間に制約が出そうだ。 |
 |
 |
D職員: |
スペック表を見ると、ほとんどがニッケル水素電池が多いようです。 |
 |
 |
C主任: |
いや、この資料によると最近ではリチウムポリマー電池がいいようだ。 |
 |
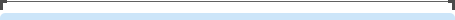 |
このあたり、千葉工業大学の小柳先生に聞いてみました。先生のロボットで言えば、03号機までが水素ニッケル電池、04号機以降がリチウムポリマー電池になっているとのこと。単純にほぼ同じ性能の両者を比較するとこうなります。
|
 |
上:水素ニッケル電池
下:リチウムポリマー電池 |
ご覧の通り、リチウムポリマー電池は「小型」というメリットの他、出力電流が大きいため例えばモータ起動時に大電流をそちらに取られても制御ユニットがダウンする心配がないというメリットがあります。特に小柳先生のロボットは、制御ユニットにOSを搭載しているため、一度ユニットダウンすると再起動に時間がかかり、ロボカップ競技中などではそれが致命傷になるので、なおさら大きな利点となるそうです。なお残量のある使用途中での充電も可能(メモリー効果なし)だそうです。
|
なお有線式のロボットについては「むしろそちらが現実的な選択ではないか」とのお答えでした。遠隔操作のインターフェースは人間の視野を広くカバーするパノラマビューに向かうだろうし、するとカメラも5〜6台必要になる。「現状でも容量が不足する無線式では当然それらに対応できず、有線を選択する事になるのだろう。」であれば電源も有線で供給した方が有利かもしれない。
|
|
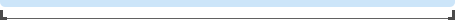 |
 |
 |
C主任: |
今回は「国際救助隊」なのだから、南極、北極も守備範囲になるし、赤道直下*10でも行動できなくてはいけない。 |
 |
 |
B主任: |
人もロボットもタフさが要求されるで。この辺は大学の皆さんに頑張ってもらわな。 |
 |
 |
C主任: |
今後開発のシナリオが幾つかあって、「バリバリⅡ」「くるくる3」など人間との協働を前提に比較的早い段階から実践で活躍させるものと、人間が行けない困難な場所での自律活動を目指す長期開発のシナリオとに分かれるんじゃないか。 |
 |
 |
D職員: |
謎の大金持ちがいるんですから、同時進行で開発できますよ。 |
 |
 |
B主任: |
やはり実践や。実践あるのみ。これで鍛えな。 |
 |
 |
C主任: |
でしょうね。どんどん災害時に出動するのはもちろん、平常時にも活用しておけば開発のテンポは相当速くなるでしょうから。 |
 |
 |
D職員: |
ということで、我々国際救助隊のロボットは日頃、ANAさんやウチで働くことで決まりですね。 |
 |
 |
C主任: |
オペレータもロボット自身もドンドン向上できるからね。 |
 |
 |
B主任: |
しかしANAさんはこの案、どない思いますやろか。 |
 |
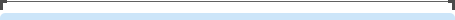 |
ロボットのオペレータについても小柳先生に聞いてみました。これまでのロボカップなどの経験からオペレータの適正について尋ねてみたところ「平常心を保てる人」という言葉が返ってきました。
「ロボットの性能をわきまえ、無理をしないこと、かっこいいことしようと思わない人」という意味での平常心と「実際の現場では悲惨な光景が突然カメラに展開される」わけでそういう点でも平常心が大切とお考えのようでした。
|
 |
| 小柳先生、また色々教えてください! |
| ©IRS |
「レスキューロボットは、被災者を発見したら、そこを動いてはいけないと思うんだ。せっかく見つけてもらったのに、被災者が不安になるからね。探索しかできないロボットとはいえ、水や食料なんかも積んでおけばいいし、何より重要なのはマイクとスピーカーだよ。肉親の励ましの声が届き、話せることがやっぱり大事なんだよ。だからロボットは大量にもっていかなきゃいけないよ。」
|
ご多忙の所、素人の我々にもわかりやすく、そして粘り強くご指導いただいた千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)の副所長である小柳先生。上のコメントはじめ、色々な意味で本当に良い勉強をさせていただきました。どうも有難うございました。
|
|
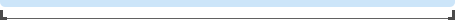 |
 |
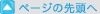 |
 |

