| 部員達一行は、新幹線に乗り〝コマツ・テクノセンタ〟へ向かった。ついた所は見渡す限り伊豆の自然に囲まれた、白い近代的なビルディング。コマツさんの最先端テクノロジーに触れ、その確かな品質・信頼性を確認できるよう、観覧スタンドから機械を見られるデモンストレーションエリアや、リサイクルに特化した、リサイクルエリアがあります。デモエリアは東京ドームとほぼ同じ大きさ。試乗体験も可能です。この豊かな自然と力強い大きな建機が共存する不思議な空間に、お話をしてくださる「ラジコン建機の鉄人」お二人がいらした。
|
 |
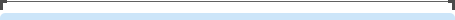 |
 |
| 大変お忙しい中をご協力いただきました |
コマツ
営業本部 市場開発部 油圧ショベル・ワーキングギアグループ
ラジコンチーム長 荒川 輝昭 氏(左)
営業本部 市場開発部 油圧ショベル・ワーキングギアグループ
ラジコンチーム 石橋 昌樹 氏(右) |
| ©コマツ |
|
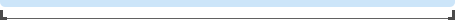 |
 |
 |
B主任: |
コマツさんはラジコンによる重機操作の分野がお強いちゅうことですが、いつごろから実用化されて、今のようなすばらしいものになりましたんでしょうか? |
 |
 |
荒川氏: |
1993年の雲仙普賢岳の噴火後の復旧活動において、ラジコン制御の無人化施工機械(重機)を実際の作業で使用したのが最初です。当時は、いつまた火砕流が発生するかわからない危険な状態での復旧作業でしたので、どうしても離れた場所からの重機操作が必要でした。 |
 |
 |
C主任: |
災害現場では、瓦礫を撤去し救助活動がスムーズに行えるような状況をつくりだす。なおかつ、救助者がすぐそばにいるってことですよね。
|
 |
 |
荒川氏: |
そうですね。なので「精度」が要求されます。相手が人となるとやはり重機に乗っての操作は慎重さ・正確さに欠けますね。なので、ラジコンを持って救助場所の「そばで見ながら」慎重に作業を行うしかないですよね。なのでラジコン仕様車が災害復旧・救助活動に有効ですよ。 |
 |
 |
C主任: |
そうなんですか。現場の実際に使っていたオペレータさんの評価はどうでしたか? |
 |
 |
石橋氏: |
まず、災害・復旧活動は長期・長時間かかるものですから、ラジコンを使うことで疲れてしまっては困ります。 |
 |
 |
D職員: |
そうですよね。じゃあ軽くて小さいゲーム機のコントローラーが理想ですね。最近の男の子は、小さいときからゲームを指でピコピコやりますしね。すぐに重機を動かすにも慣れるでしょう! |
 |
 |
A部長: |
(私の知ってる鉄人28号では大きめのリモコンだったが、時代ということか・・・) |
 |
 |
荒川氏: |
実はですね・・・ラジコンが小さすぎても疲れる、という現場からの声がありました。作業は1日8時間くらいになりますし、阪神大震災の時のように昼夜を分かたず行われることもあります。 |
 |
 |
B主任: |
けど、ゲーマー呼ばれる、あの人ら1日8時間くらい楽勝やない? |
 |
 |
D職員: |
でもですね、確かにポリフォニー・デジタルさんのグランツーリスモでも、手のひらサイズのコントローラより、本物のハンドルやペダルに近いGT FORCE Proを利用したほうが、何かとよかったなぁ。 |
 |
 |
石橋氏: |
長時間の作業を考えると、ある程度の大きさ・重さ・ちゃんとした姿勢がとれることが作業には1番いい環境なんです。 |
 |
 |
B主任: |
なるほど。そうかもしれん。 |
 |
 |
荒川氏: |
我々も一度は小さくて軽いラジコン装置を開発していたのですが、現場からの声を聞き、今ではあえて大きさを大きくし、その分壊れにくいヘビーデューティ型にしています。 |
 |
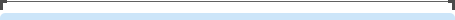 |
 |
| 送信機(持っている時) |
| ©コマツ |
|
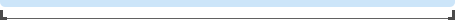 |
 |
 |
C主任: |
逆リュックサックみたく、前側に肩紐をかけるんですね。これなら長時間でも肩こらなそうですね。危険な災害現場では、いざという時には両手も使えることも重要でしょうし。 |
 |
 |
B主任: |
ランドセルを前にかけて「ロボコン」言いながら遊んでた、小学生時分を思い出すわ。 |
 |
 |
石橋氏: |
送信機の胸版はコマツオリジナルです。これがあることによって送信機が体に固定され微操作性がよくなり、より安全に重機を動かすこともできます。 |
 |
 |
D職員: |
確かに紐を肩から下げているだけだと左右に操作の部分が揺れて安定しませんね。精度を出すためのノウハウが詰まった胸板ですね! |
 |
 |
A部長: |
(やはり大きくてよかったのか。この胸板もあれば正太郎君ももっと操作しやすかっただろうな。しかし、偶然とはいえ、漫画と似るもんだ。)
|
 |
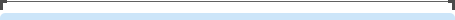 |
 |
| ラジコン(詳細部) |
| ©コマツ |
|
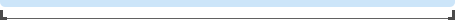 |
 |
 |
荒川氏: |
操作がしやすいようにも工夫されています。最近はタッチパネルのように、On-Offをランプで示すものもありますが、それではいちいちラジコン装置を見て確認しなくてはいけません。当社のものは、まず、指で押すようなボタンは緊急停止用のボタンしかありません。理由は単純で、操作に慣れたオペレータさんにとっては、スイッチに触れただけでどちらにスイッチが入っているかがわかるのです。複雑な操作が要求される現場では、指で押すスイッチばかりだとラジコンを送信機見ながら操作をしなくてはいけませんよね。 |
 |
 |
石橋氏: |
この操作レバーの長さにもこだわっています。大人が握りやすいように80mmの長さにしています。これも開発当初から苦慮したところです。 |
 |
 |
B主任: |
いや、気づかんかったなぁ。確かに短すぎても細かい作業のときに操作しにくいな。で、周りについている銀色の鉄の棒、飾りでっか? |
 |
 |
荒川氏: |
違いますよ。これは、操作中にラジコン送信機にぶつかって重機が誤動作しないように、ガードするためのものです。 |
 |
 |
D職員: |
なるほど。人ってリュックとか、カバンとか、体にプラスされた大きさをうまく把握できずに、ぶつけちゃったりしますもんね。 |
 |
 |
荒川氏: |
それだけではないんですよ。操作をする際に手を安定させるためでもあるんですよ。送信機を持っている方の手元を見ていただけたら分かりますが、ガードに小指を引っ掛けていますよね。このように指を引っ掛けたり、手を乗せたりして安定させています。これによって、細かい操作が可能になるのです。この形状に決めるのに現場でオペレータさんの声を聞いて改良しました。 |
 |
 |
C主任: |
この銀の棒が1番単純な作りなのに、1番重要かもしれない。1つで2役ですね。 |
 |
 |
B主任: |
操作には免許は必要なんですか? |
 |
 |
石橋氏: |
車両系建設機械の免許が必要です。操作してみます? |
 |
 |
B主任: |
いや免許もっててよかったわ。是非お願いします。 |
 |
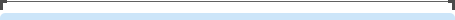 |
 |
| ラジコン仕様車 |
| ©コマツ |
|
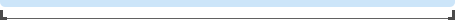 |
 |
 |
B主任: |
こんなに大きな重機を、大食いの人のお弁当箱くらいのラジコンで動かせるなんて機械の革命や。それに手元と重機の動きに操作の遅れが全然感じられないやないですか。
|
 |
 |
C主任: |
体験させていただくと、さらに素晴らしい技術であることが実感できますね。 |
 |
 |
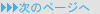 |
 |
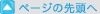 |

