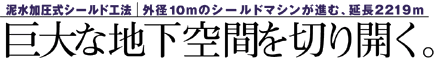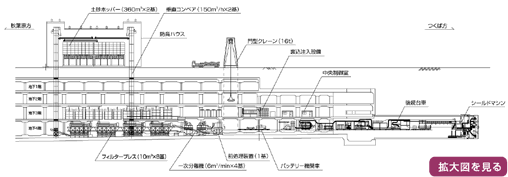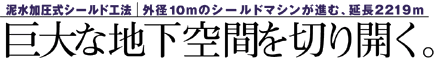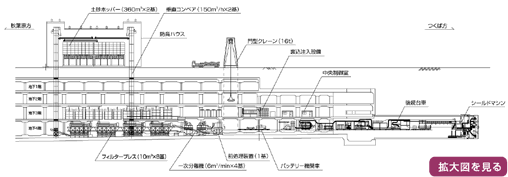|
 |
2002年4月、新浅草駅から南千住駅へシールドマシンがスタートした。掘進スピードは1日約10m。取材した2003年1月14日は、ほぼ中間地点の1190mだった。
この工事は、可燃性のメタンガスを含む礫(れき)層を1400m掘進する。そのため、マシン内の電気機器類を防爆仕様にし、計測器を付けてガスの探知を徹底した。
機電主任の森山は、設備の計画から据え付け、運用、撤去まで、機電のすべてを担当している。シールドトンネルの工事は、すべての工程が連動しているため、1カ所でもうまく動かなければ、すべての作業が止まる。コンピュータ制御をしているため、故障の可能性も高い。機電担当者の役割は大きく、責任が重い。
「どんなに考えて計画を立てても、工事が始まってから起こる問題をすべて予測することはできません。予期できないことが起きたときが一番大変です」と森山は言う。
§
シールドマシンが掘進した後、トンネル内への地下水や土砂の流入をセグメントで防ぐ。最初の249リングは金属製のダクタイルセグメント。その先は、RCコッター・クイックジョイントセグメントである。
所長の森嶋は「コッター・クイックジョイントセグメントが採用されて、作業効率が大幅にアップしました。最後に大きな山場がありますから、これからが大変です。沿線周辺の方々と現場の安全を確保して、『誠実・意欲・技術』を結集して掘進管理をし、施工精度を向上させています」と語った。
§
土木担当の次長である正岡は、技術の責任者として、日本鉄道建設公団と前田JVの太いパイプ役を果たしている。「これから民家の下の豆腐のように柔らかい地層を掘進します。さらに、南千住駅の手前300mの間は、工事の最大の難所となります。事前に計測を行い、掘進による地中への影響を確認し、この区間におけるシールドマシンの最適な進め方をぎりぎりまで検討します」と正岡。難工事に向けて、緊張感が高まる。 |