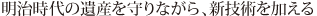
本河内低部ダムは、神戸の布引五本松ダムに次いで、日本で2番目に建設された重力式コンクリートダムである。堤体の表面は、上流側は天然石張り、下流側は明治時代には貴重な材料だったセメントで作られたコンクリートブロックが全面に張られている。この近代土木遺産を大切に守りながら洪水機能を持たせる工事を行うことが、前田JVの使命である。
浄水場を挟んで上流に高部ダムがある。その高部ダムの貯水利水容量を約36万m3から38.6万m3に増量して、水道用水を確保する工事を完成させた後、低部ダムに洪水調整機能を付加する工事が前田JVに発注された。
着工前に長崎県が水抜きをしたが、その後二度の大雨で満水状態に。そこで、前田JVが2カ月半をかけて再度水抜きを行い、湖底に溜まった堆泥を石灰系固化剤を用いて改良し、約3万m3の泥を工事用道路の盛り立てなどに再利用することから建設工事を始めた。

水道専用ダムに洪水調節機能を付加するために、日本初の構造である「竪坑型トンネル式洪水吐き」が採用された。
この構造は、上流側に呑口竪坑、下流側に減勢竪坑を建設し、その間をダム底から約20m下の位置に、長さ96m、仕上がり内径4.5mのトンネルで繋ぐというものだ。
トンネルの掘削は、幅5.4m~6.3m、高さ5.3m~6.2mの馬蹄形だが、覆工は全線円形(Ø4.5m)の鉄筋コンクリート造で設計されている。2009年9月14日に無事貫通し、現在、覆工コンクリートを施工中である。
2009年11月には、呑口竪坑本体はトンネルの上部あたりまでコンクリートを打設し、減勢竪坑本体はトンネルから少し下がったところまでのコンクリート打設が進んでいる。
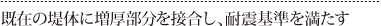
「竪坑型トンネル式洪水吐き」の建設と同時に、既存のダムを現在の耐震基準に適応させるために、堤体の上流面側に増厚工事を行う。
2009年11月5日から新設堤体のコンクリートの打設を開始。基礎掘削したあと、岩盤と堤体との隙間を埋めてある三化土(※)等を除去し、岩の部分をスポンジと雑巾で丁寧に清掃したうえで、コンクリートを打設している。
品質の条件は新旧堤体の一体化である。要求された品質を確保するには、既存のダムに打ち込む構造鉄筋の長さ・太さ・間隔を決めることが重要だ。そこで、事前に現場試験を行い、その結果を設計に反映させている。
増厚工事の完了後、常時満水ラインより標高の高い部分に天然石を張る計画だ。堤体の表面は景観に影響を及ぼすため、現在、石材や目地の色を慎重に検討している。
また、高部ダムの新旧堤体間の埋め戻しも低部ダムの工事項目に含まれている。2009年11月末時点で、全体で3万m3のうち約1万m3の埋め戻しが完了した。
工事完了後、工事用道路を撤去した土砂と、貯水池を拡幅掘削して出る約6万m3の土砂を、15km先にある大村湾埋め立て地に運ぶ予定だ。
このようにして、2011年1月の完成を目指している。
※三化土は「セメント代用土」とも呼ばれている。長崎の三化土には、赤味のある玄武岩風化土(玄武土)が使用されている。
|

