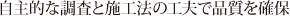
前田建設は、熊本合同庁舎A棟(地上12階・地下1階)建築工事を単独受注した。敷地は月星化成の工場跡地である。工場解体後に行われた二本木遺跡群の埋蔵文化財調査の資料を施工前に入手して、既存基礎の位置を図面化し、杭や山留めに干渉するものを先行撤去し、掘削時にはすべてを撤去した。また、受注前の地下ボーリング調査は建物中央の1カ所のみだったので、自主的に5カ所の調査をして支持層が傾斜していることを確認し、当初の山留め計画を見直した。
2008年7月8日に着工。まず山留SMW(※1)工法で遮水壁を設置し、泥土処理には泥土低減工法を採用した。10月に地下掘削を開始し、ディープウェルで地下水位を下げながら工事を進め、半年間にわたり3万m3の地下水を汲み上げた。基礎杭には地中熱利用杭を採用。エコパイル(鋼管)の先端に蓋をして、鋼管の中に水を入れ、空調に地熱を利用する計画だ。
※1 SMW工法とは土(Soil)とセメントスラリーを原位置で混合・撹拌(Mixing)し、地中に造成する壁体(Wall)の略称。
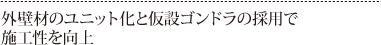
柱の鉄骨は3フロア分で1本、全部で5節とし、鉄骨の建方は、建物を東と西に分けて、東側を建ててから西側を建てるという方法で施工。外壁の品質を確保するために、鉄骨建方の精度には細心の注意を払った。そして、鉄骨を建てたあとを追うように、下の階から床コンクリートを打設していった。
外壁には、タイルのPC版とアルミキャストという2つの建材を採用。当初、アルミキャストは足場を組んで外から張る仕様だった。しかし前田建設は、アルミキャストもユニット化すればPC版と同様に無足場で施工できると考え、鉄骨・鉄筋コンクリート造の1・2階のみ足場を組み、鉄骨造の3階以上には足場を組まず仮設ゴンドラを併用して施工することを提案。この工法が採用された。
工場生産できる部分はできるだけ工場で作って精度を確保し、現場では設置するだけにする。このように工夫をして「良いものを、早く、安全に」施工している。

2010年1月に防火水槽とオイルタンクを設置し、3月には外壁のシーリングを完了。4月には内装や配管などを施工した。
新庁舎には6官署が入居するため、発注者である国土交通省九州地方整備局はもとより、6官署からも個別にご要望をお聞きし、設計が固まったフロアから順に施工している。また、屋上に気象台の天気観測デッキを設置するなど、各官署独自の施設も設置している。このようなことから、内装工事はすでに設計や仕様が決定しているエレベーターホールやトイレなど共用部の施工を先行した。
また、市電電停と駐車場の双方から出入りしやすいよう2カ所に設けたエントランスも施工中である。
2010年11月30日に完成し、品質検査を経て、入居が始まる予定だ。新庁舎が九州の行政サービスの拠点となり、地域のみなさまに親しまれる建物になることが期待されている。
なお、この現場では前田建設の「環境経営」の理念に基づき、泥土や排水の処理から、資材の調達先の選定や搬入方法など、施工に関わるすべてに一歩踏み込んだ環境対策を講じ、職員と協力会社が一丸となって取り組んでいる。その成果が日本土木工業協会に認められ、表彰された。今後はこの取り組みを前田建設全体に水平展開し、「環境経営」を推進しようと考えている。
|

